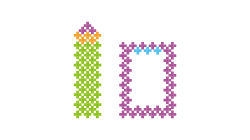
「見ること」と「話すこと」
佐々木亨
日時/2022年7月30日(土)13:00~16:45
場所/北海道大学文系講義棟6番教室

プログラム
開会の挨拶/寳金 清博(北海道大学総長)
パネリスト/浅川 真紀(あべのハルカス美術館上席学芸員)、
緒方 泉(九州産業大学教授)、
小篠 隆生(北海道大学工学研究院准教授)、
佐々木 亨(北海道大学文学研究院教授)
司会/今村 信隆(北海道大学文学研究院准教授)
閉会の挨拶/藤田 健(北海道大学文学研究院長)

今村
講演では、ミュージアムや教育の現場では、人は時間をかけて成長し、世代を超えて知識や経験を受け継いでいくということを話されていました。私もこの「時間をかけること」が幸福を考える上で重要なポイントではないかと思います。
浅川
私は美術に憧れて、それを伝えたいという思いから学芸員としてスタートしましたが、自分自身の成長とともに変化してきたように思います。
学芸員は人間の創造物の「良さ」を伝える仕事をしていますが、絶対的な価値判断はありません。その時々で「共有したい」ものを示しつつ、本質的に大切なものを考え続けることが重要だと思っています。
その時の自分や時代の変化に寄り添い、提示すること、そして自身が変化していくことが学芸員という仕事の面白さではないかと思っています。
小篠
東川では、施設の整備やその結果に求めるものとして、「丁寧な暮らし」をみんなが体感したり、見つけたりすることがテーマになっています。全てのプログラムの企画に、この考えは入っています。
例えば、2014年の小学校開校から約8年の間に、子どもたちは世界的な彫刻家・安田侃の名前を自然に覚えるようになりました。これは単なる知識の習得ではなく、パブリックスペースである都市空間を使って行う展覧会が増えてきた結果として、「公共性」というものを考えるようになったと思っています。
つまり、施設の中だけでなく、町全体に眼差しが向くようになり、日常生活も含めた「丁寧な暮らし」にシフトしてきているのではないかと思います。子供たちは、文化的な情報発信を自分たちの役割だと理解するようになってきているのではないかと思っています。

今村
ミュージアムの価値を世の中に、いろんなレベルの人たちに伝えていくときに「数値による測定(エビデンス)」や「言葉によるナラティブ(ストーリー)」といった2つのアプローチを組み合わせることで、より説得力のある評価が可能になるのではないかと考えます。「ミュージアムの価値を探る方法」についてどのようにお考えですか。
緒方
「丁寧さ」が重要だと考えています。美術館や博物館では時間の制約により、鑑賞が急ぎがちになり、丁寧に見る習慣が定着していないように感じます。
ミュージアムに何度も訪れることに意味を持たせられれば、展示空間での対話が重要な要素になると思います。そして、展示空間の中で自分がどのように感じたのか、例えばリラックス効果があるのか、不安感が解消されるのか、エネルギーを得られるのかといった点に注目することもできるでしょう。
福岡市の美術館で行った作品ごとの調査では、古美術などではエネルギーの変化はないけれども、抽象的な作品ではエネルギーの立ち上がりが大きいというデータが出てきました。イタリアの論文でも同じようなデータが出ており、事例が積み重なると、気分に応じて美術館を選ぶことも可能になるかもしれません。やはり、ミュージアムの新たな価値を生み出すためには、丁寧なデータの蓄積が重要だと考えています。
今村
イギリスのミュージアムの「ミュージアムがライフを変える」という標語のライフには、生活と人生という意味があり、生活を積み重ねていくと人生が変わっていくことになり、エビデンスを積み重ねることが大切だと感じました。
佐々木
「エビデンスを積み重ねること」は評価を行う人間として、永遠の課題です。
自分自身がミュージアムを評価する場合も、数字だけの評価には限界があると感じています。市民もそれを期待していないし、ミュージアム側も改善に活用しにくいのでは意味がありません。
評価では、行動変容や成長といった質的なアウトカムが重要であり、単なる数値化では不十分だと思っています。変化の内容や深さを伴いながら、数量、アウトカムの深さをテキストで捉えながら、数量も測るくらいが、1番適切な落としどころかなと思ってます。まだ、全然できてないですが、まずは質ありきだと思っています。
今村
緒方先生のご研究をお聞きし、美術館の資料である作品という「もの」自体が幸せをもたらす一方で、ミュージアムというフォーマットそのものが幸せや何か安心感をもたらすのではないかと感じました。
ミュージアムという環境が持つ幸福に繋がるような特質、特に環境が持つ面白さや強みについて、どのようにお考えでしょうか。
小篠
ミュージアムを設計する場合、外部との接続をどれだけ確保できるかという点を重視しています。ミュージアムという環境の範囲を拡張することができ、異なる利用方法や展示の仕方、意味付けが可能になる「余白」を持たせることが大切だと思っています。例えば、屋外展示のような物理的な接続領域を設けることが大事だと強く思っています。
今村
「せんとぴゅあ」には独特の居心地の良さがあるように感じます。私は東川町の町民ではありませんが、そこでは何か面白いことが起こり、人の動きがあって、皆が楽しそうにしている。外に開かれていながらも、吹きさらしではなく、包まれるようにとても心地よくて「場所の持つ気持ちよさ」があるように思います。
小篠
ミュージアムの中では楽器を演奏はできないのですが、大きな庇の下は、楽器を演奏したり、ひと休みしたり、リラックスできるスペースとして思い思いに利用しています。
新たな使われ方が生まれているミュージアムに付随する「中間領域」という空間があることがすごく大事なんだと思っています。

浅川
意図しない過ごし方を誘発できるというのは、とても素敵だと思います。
建物はある程度そこで過ごす人の行動を想定して設計されますが、実際にできてみると想定していなかった居心地の良さもある一方、逆に居心地の悪さもあって、本当に難しいと実感しています。
私は美術館の開設準備から関わっていて、「ここをこうした方がいい」と言えた部分もありましたが、実際に運用してみると、やはり足りないところが出てくる。意欲的な新しい美術館を作ったはずでも、思ったようにいかない部分があるのは日常茶飯事です。
私は建物の設計はしませんが、展示の設計はします。その際、展示空間は一時的なものですが、シチュエーションの部分、お客さんの心や体、目や脳がどう動くかをきっちり想定して設計しようと思っています。ストレスなく作品と向き合えるような環境を整えるというような「幸福の小さなきっかけ」が大事だと思っています。建物全体の設計という大きな枠組みと、お客さんの細かな行動を想定した設計、その両方が必要だと思っています。
今村
設計において、どこまで意図的にコントロールし、どこまで余、「遊び」を残すか、さらには意図しないことをどこまで許容するかのバランスが、居心地の良さに関わると思いますが、いかがでしょうか。
浅川
来館者は、想定外の行動をするので、日々展示の調整をしています。
緒方
このコロナ禍で、実際に美術館に行って作品と直接向き合う機会が減ってしまいました。学校でも集団閉鎖が続き、そのまま夏休みになりました。
そこで、オンライン鑑賞教室を開き、大学美術館のコレクションを紹介するだけでなく、作品の中の人物のポーズを真似て体を動かしたり、作品から聞こえそうな音をカスタネットや身近なものを使って表現したりすることで、自分自身の鑑賞体験というものを表出させるようにしています。
ものを見ると、様々なことを感じ、体の中で、頭で感じて考える。そしてそれを「見る」「話す」「書く」といった行動に加え、実際に「歩く」といった身体的な動きで外化する。その内化と外化の往還運動の中でものと向き合うことが、理解の深さに繋がると考えています。オンラインでも、こうした内面的な気づきと外への表現を往復するプログラムを考えているところです。
今村
「歩く」というのは、1つキーワードとして良いかもしれませんね。
また、ミュージアムは物理的な空間として考えがちですが、むしろ発想や考え方としてのミュージアムがあるのではと思いました。オンラインでもミュージアムらしいアプローチが可能だと感じました。
佐々木
ミュージアムは「見ること」に特化していますよね。でも、大阪の国立民族学博物館のミュージアム展では視覚障害者向けに「触る」「聞く」に特化していました。その場合、展示空間のあり方もかなり違ってくると思います。内化や表出についても視覚だけに固執する必要がないので、ミュージアムの可能性ってもっと広がると感じました。

大澤
私は、ミュージアムグッズの研究と仕事をしています。「外化」の話を聞いて、見る・話す・歩くといった行為に「物を買う」ことも含められるのではと考えました。消費する行為は、展示を見ることではなく、自分の欲望や内化したものを反映しやすいのではないかと考えます。 この点について、皆さんの意見を聞きたいと思っています。
緒方
作品を見て展示空間を歩き、お気に入りの作品と出会い、佇むことで内化と外化が往還する。その記録を残す行為の一つにミュージアムショップに向うことがあり、「買う」という消費行動に繋がる。そう考えると、消費行動も外化の一つとして含められるのではないかと思いました。
浅川
あべのハルカス美術館のショップはとても充実していて、売上も重要な収入源になっています。でも、単なる売れればよいということではありません。
気に入ったものを買って持ち帰るあるいは誰かに差し上げることで、その体験を記憶に残したり、人と共有したりできるショッピングという行為はミュージアムの幸福体験の一環として位置づけられると思います。グッズ開発もミュージアム体験を進化させる視点で考えることが大切だと思っています。
卓
私は、博士課程で地域とミュージアムの連携による社会的効果を研究し、その後、シンクタンクで研究員として働いてきました。そうした経験から、まちづくりや防災、福祉などの政策の最終的な目的は、国民の安心感や幸福に繋がることだと考えています。その中で、ミュージアムも何らかの形で役割を果たしているはずですが、あまり認識されていません。私は他分野との対話や連携の可能性を探りたいと考えています。
浅川先生の発表で、最後に「祝福」という言葉が出てきました。意図せずに、ポジティブな方向に繋がっていけたら、それがミュージアムの価値になると感じました。
浅川
「祝福」という言葉が、自分の考えにあてはまります。他者を幸せにし、受け継いでいくことが「祝福」だと思うのですが、ミュージアムもまた、人々を繋ぐので、「祝福」に重なると思います。幸福は祝福し合うことの連鎖が次の時代へと繋がっていくことで達成されると思います。
ただ、それを続けていくには、ミュージアム自体の「健康」と「サステナビリティ」も大切だと、とても思います。民間企業である「あべのハルカス」に勤務して、収支の厳しさを実感したので、適切な収益の循環が持続的な運営、ミュージアムの幸福に繋がると思うようになりました。コロナ禍を経て、ミュージアムの「健康」をどう守るかを考えるようになりましたが、本日のシンポジウムでもいろいろ示唆がありました。
今村
体の健康、精神の健康に文化の健康もあると考えられますね。

今村
ミュージアムには癒しや楽しさだけでなく、不快に感じる作品や情報も含まれることがあり、幸せを前面に出すことで、そうした作品が埋もれてしまうのではないかという懸念がありますが、先生方の考えを聞かせてください。
緒方
もちろん、私も同じ意見です。様々な作品を展示する空間として博物館や美術館は存在するので、必ずしもすべてが癒しを与える作品を展示するわけではないと思います。作品の調査や研究を通じて、それぞれの評価を充分に行ったうえで展示しているわけですから。
ただ、これまで「博物館に来ることでどうなるのか」という議論はあまりされてきませんでしたが、最近はスイスやイタリア、イギリス、アメリカ、ニュージーランドなどで、こうした博物館学研究が進んでいて、データも出てきています。本日のテーマである「幸福感」だけではなく、「どんな作品を置くと、そこにいる人がどう感じるのか」という話まで進んできています。
展示や空間のあり方を数値化して評価する方法もあり、論文には作品の種類や内容までもすべて提示しようという研究の流れになっています。なので、私は「不快に感じる作品を排除する」ことはまったく思ってなくて、むしろ「その作品と向き合ったとき、人はどんな時間を過ごすのか」を捉えるためにも、生理的・心理的な測定を取り入れていくのがよいのではと考えています。
今村
緒方先生の話の「データを幅広くとり、展示のあり方の様々な可能性を検証する」実際の展覧会の例として森美術館で開催された「地球がまわる音を聴く」展(2022年6月29日~11月6日)を紹介します。
この展覧会は、幸せをテーマにしながらも、ドメスティックバイオレンスや迫害といった人の痛みに向き合う作品が多く展示されています。傷と向き合う時間は必ずしも癒しにはならないが、ミュージアムの重要な役割の1つであり、ウェルビーイングの一つとして示されていた点に感銘を受けました。
浅川
「せんだいメディアテーク」の鷲田清一先生の「理解し合えない前提での対話」という考え方に共感しました。事実も受け止めきれない、理解しきれない前提で見るところもあるのではないかと思いました。
幸福も簡単に手に入るものではなく、なかなか手に入らないのが幸福という前提もあると思っています。「受け止められないものを受け止めてみる、理解しきれないものを理解しようとしてみる」といった感じでしょうか。
人類や世界を大きく捉えて自分の中に吸収するように、この絵の中にその幸福がある。そんな意味を感じました。とても漠然としていますが、そんなことを考えました。
佐々木
広島平和記念資料館のリニューアルに委員として関わりました。他のミュージアムのリニューアルの委員会に参加した場合、たいていは展示業者がすでに決まっていて、委員は微修正を加える程度の立場が多いのです。しかし、広島は全然違って、本当にガチの議論が繰り広げられていました。いろんな団体の人が参加して、何回やっても議論が終わらないくらい真剣で、「こんなに話し合ってたら、展示はいつできるんだ」と思うほど深いのです。
このような「ハッピー、幸せなんだ、楽しい」だけじゃないものを展示する時こそ、このプロセスがすごく大事で、過去の展示を振り返って、「どこが良かったのか」「本当に伝えたいことは何なのか」を徹底的に精査していく。その過程自体が、ある意味で「幸せに至るプロセス」だったんじゃないかと思います。だからこそ、今の展示が実現したのだと感じています。

小篠
ミュージアム=展示と決めつけると「ハッピーじゃない展示はどうする」という話になると思います。
知ってる方もいると思いますが、「生きた本の図書館」ってご存じですか。
人が本なのです。人を選んで30分くらいその人の話を聞く、これは一種のセラピーなんです。話す内容も必ずしもハッピーな経験ばかりじゃなくて、人に話しづらいことを語ることもあります。
僕はイタリアで見せてもらいました。イタリアは精神病院を廃止している国なのです。精神病院を廃止してる国の中には、第三者と話すことで心が開かれていく仕組みである図書館があり、医療機関に近い役割を果たしています。
何か「展示物」としてカッチリ形にするのが難しいことも多いのですが、人は何かのきっかけで話し出すと、それが繋がっていくこともあると思います。そういう「人の語り」や「対話」そのものを、広い意味で「展示」と考えてもよいのではないかと考えています。
今村
精神医療では、クライアントが言葉にすることで治療効果が生まれることがあります。
社会全体でも「展示」という形で言語化することが、もしかしたら治療的な効果を持つのかもしれない。そして、それが、ミュージアムの役割でもあると本ディスカッションを通じて理解することができました。
文字起こし・編集:
森沙耶・岩瀬峰代(株式会社サイバコ)