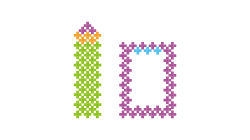
「見ること」と「話すこと」
佐々木亨
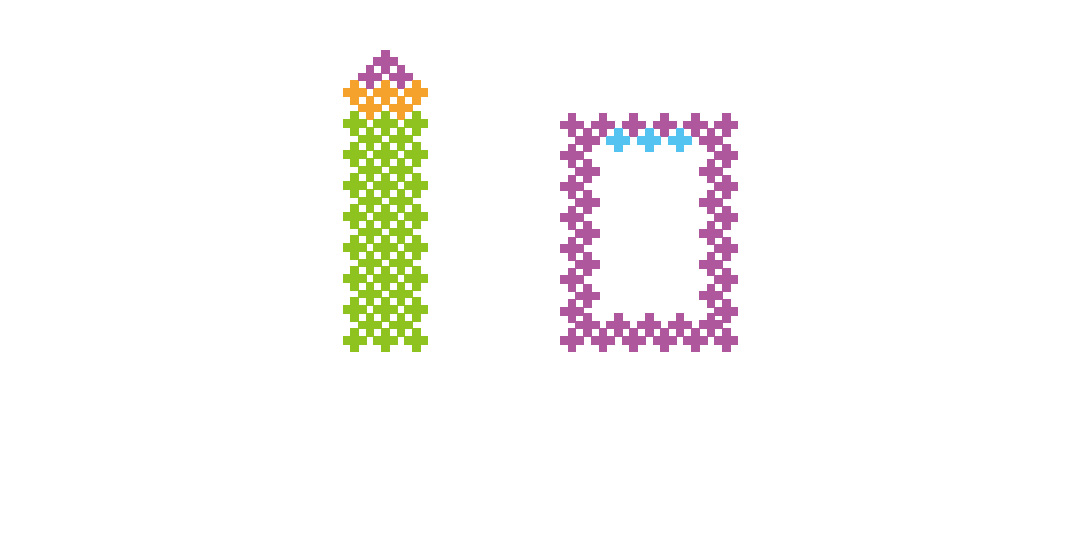
ミュージアムの来館者調査といったときに、どんな調査形態をみなさんは思い浮かべるでしょうか。展示室の出口付近に「お客様の声をお聴かせください」という控えめな誘い方をしているパネルの前に置かれているアンケートをイメージする方 もいるでしょう。最近では、出口のパネルに印刷されたQRコードをスマホで読み込んで、アンケートの設問に回答する場面を思い浮かべる方も多いかも知れません。
私は、来館者調査をミュージアムから依頼されることがときどきあります。その場合、調査の目的をしっかり伺った上で、どんな調査手法を選択するのがよいかを双方で検討していきます。最近、あるミュージアムで実施した来館者調査では、展覧会の来館者に対して了解をいただいた上で、展覧会場内での観覧行動についての観察調査、観覧後のインタビュー調査、さらに来館前後それぞれ一ヶ月間の生活実態に関するアンケート調査を実施しました。併せて、この一連の調査対象者以外には、展覧会の出口で全員に声かけした上で、アンケート用紙への記入をお願いしました。これだけ多くの調査手法を用いて、来館者の実態を調査したので、目的に沿った有効なデータがたくさん収集できました。
この調査では、観察調査、インタビュー調査、アンケート調査の3つの手法を組み合わせています。つまり、1)見ること、2)話すこと、3)きくこと、です。お客さんが展覧会を観ているおおよそ1時間の行動を観察させてもらい、観覧後にあらかじめ用意していたテーブルに座ってもらい、展覧会場での動線や同伴者との会話発生箇所を記録した観察データを見ながら、20?30分程度インタビュー項目に従ってお話しを伺います。しかし、しばしばその項目から逸脱します。いや逸脱させています。例えば、同伴している孫とのこれまでの関係性と、自分自身の過去の仕事体験から、いまここに二人でいることの必然をゆっくりと語ってくれた60歳代の女性がいました。これはまさにお二人の人生にとってミュージアムはどんな意味を持っているのかを話された瞬間でした。ほかのミュージアムでも出口でインタビュー調査のみを行うことがありますが、このような深い思いを伺うことができたという経験がありません。
この一連の調査をミュージアムで実施して、私はあらためて「見ること」と「話すこと」を同時に行う大切さを実感しました。つまり、そばに立ち来館者を見ること、向かい合って話すことからわかることが、いかに深くて豊かであるかということです。
今回、プラス・ミュージアム・プログラムでは、卓先生を中心としてプログラムの教員が、北海道内のミュージアムに直接伺い、展示を見たり、バックヤードを見学したりしながら、インタビューを続けています。つまり、フィールドワークをしながら、当事者と対話していると言えます。文化社会学者の佐藤郁哉氏は『フィールドワーク-書を持って街に出よう(増訂版)』(2006)の中で、インタビューのさまざまなタイプについてこのように書いています。
サーベイなどで用いられるフォーマルなインタビューの場合には、就職面接のように聞き手がワンランク上で、話し手がそれに対して一段下におかれ、「聞き出す」「情報を収集する」という性格があります。一方、フィールドワークにおけるインタビューでは、この立場が逆転し、「教えてもらう」「アドバイスを受ける」という表現がふさわしいインタビューとなります。加えて、聞き手が必ずしも「インタビューアー」というようなフォーマルな役割で質問しているわけではなく、一対一という改まったフォーマルなセッティングで行われるわけでもないとしています。つまり、いろいろなところで折に触れて質問しています、と。
本プログラムのインタビュー・シリーズは、まだはじまったばかりですが、ミュージアムの現場に直接伺い、「見ること」と「話すこと」を大切にするフィールドワークを基本として、展開しています。このことで、それぞれのミュージアムについてのインサイトが深まり、それを広く共有することで、ほんとうの意味での「対話」と「寄り添い」が実践できるのではないかと、私は信じています。