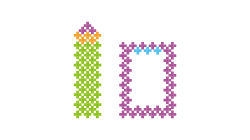
「見ること」と「話すこと」
佐々木亨

平成10年にオープンした七飯町歴史館は、歴史・民俗だけでなく、地域の自然、産業なども扱う総合博物館である。年間3、4回ほどの企画展や自然観察会、歴史講座など開催している。また、学習サービス室には約5000冊の蔵書をもつ図書の閲覧スペースが併設されており、貸し出しも行っている。歴史、自然や民俗など幅広いジャンルの図書を毎月追加している。今回のインタビューでは、博物館の業務全般を担当する同館の山田央学芸員に話を伺った。
七飯町歴史館は「町民の研究室」というコンセプトを掲げ、ミュージアムの展示や活動を通じて、「気軽に自分の知りたい分野に関して扉を開けられるような場所」になることを目指している。山田氏は、地域の人々の学びを支えるためには、現在の七飯町について収集・記録することが重要であると語った。具体的に、地域にいる自然観察員とともに町内の植物を採集し、腊標本を作製してデータベース化する活動のほか、昆虫の採集、標本化も行っている。これらの情報資料が蓄積され、ミュージアム内外で活用されることによって「博物館自体がデータベースの核になる」と期待している。
また、見学者が実物に触れたり、体感したりすることを重視し、郷土史研究会、来館者の様々なニーズに柔軟に対応している。観光客からの要望にも応え、開拓使や牛乳の歴史について話すこともあるという。

山田氏は、ミュージアムが持つ地域の歴史、自然に関する情報を使ってもらい、より高い正確性を持ったレファレンスを行うことがミュージアムの役割の一つであると話した。
地域のブランディング化において、ミュージアムが情報の提供と監修の役割を果す事例として、七飯町では産業が主に農業であり、リンゴの商標登録を進める際に、七飯町のリンゴ栽培の歴史や果樹栽培の特徴に関する情報提供を行ったことを挙げた。
また、地域から文化財の保存に関する相談も多数寄せられている。2013年に閉館した男爵資料館の建物は大正期に導入された木製サイロ、牛舎などがあり、当時では最先端だった蒸気トラクターも収蔵されている。その一部の展示物は、七飯町の道の駅にある男爵ラウンジに移されたが、その他の資料については、七飯町歴史館は男爵芋や川田良吉に関する資料を収蔵されているため、文献資料は同館が引き受けることになった。しかし、建物の移設は難しいということもあり、記録だけでも残すために、北海道博物館に相談し、建物の記録と関連資料を散逸しないように後世に残す方法を模索している。
地域の歴史と文化財の保存において、ミュージアムは重要な役割を担っており、各方面の専門家を繋ぎ、地域の人々とともに模索していくための場を作っていくことが必要だと山田氏は考えている。
山田氏は地域課題の解決において、ミュージアムが果たすべき役割について、「文化力を上げること」であると話した。
七飯町歴史館では、小学校5、6年生を対象とした体験プログラムを行っているが、コロナ禍で募集上限を10名程度に減らし、少人数での開催になった。参加人数を減らすことによって、同じ目線で子供の興味に沿ってゆっくり対話する時間が増えたと実感しているという。このような交流を通じて、ミュージアム好きな子供が増え、ミュージアムを含めた文化施設を身近に感じ、ミュージアム・リテラシーが育まれることに期待している。

(執筆:卓彦伶)
取材日:2023年1月25日