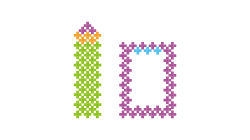
「見ること」と「話すこと」
佐々木亨
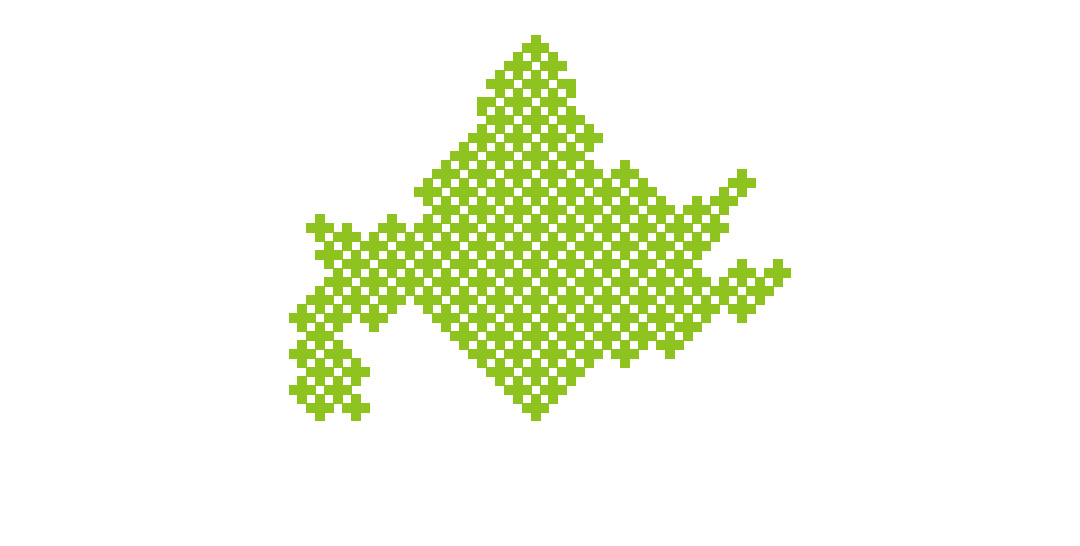
北海道は広い。諸外国と比べればそうでもないと感じられるかもしれないが、それでも日本のなかではかなり広い。九州と四国を合わせたよりも、まだ大きいのだという。日本全土の面積のうち、実に5分の1ほどを占めるのが、北海道なのである。
この広さは、観光で訪れる方たちの眼には、魅力的に映るかもしれない。ただ、住むとなるとなかなか大変なことも少なくない。確かにJRや都市間バスの事業者も頑張ってはいるが、それでも広い北海道を隈なく網羅しているかというと、決してそうではないだろう。おまけに長く手ごわい冬もやって来る。大雪、地吹雪、路面の凍結。速度規制に通行止め。さまざまな気象上の困難が、公共交通機関にも、自家用車を運転するドライバーにも、襲いかかる。
わたしたちがこうした北海道の広さを改めて痛感したのは、2018年度から2020年度にかけて実施した、北海道大学学芸員リカレント教育プログラム(通称「学芸リカプロ」)においてであった。これは、北海道内のミュージアム学芸員や関係者とともに学び直しのための場をつくろうとしたプログラムだったのだが、このとき事業遂行上の大きな妨げになったのが、ほかならぬ距離の問題だったのである。参加者のなかには、たとえば、北海道の釧路市や伊達市、倶知安町や鹿追町といった地域で活躍されている学芸員の方たちがいた。ところが、これらの場所から北海道大学がある札幌市まではいずれも相当な距離がある。一番遠い釧路市から札幌市の距離は約300km。単純にいえばこれは、東京から仙台・新潟・岐阜などに行けてしまうほどの距離なのである(しかも札幌-釧路間には新幹線やリニアが走っているわけでもない…)。参加者は、忙しい本務の合間を縫って、これだけの距離を移動してわざわざ来て下さっていたのだ。もっとも、最終年度の2020年度には新型コロナウィルス感染症の蔓延にともなってほぼすべてのプログラムがオンラインで行われるようになり、距離はさほど問題にならなくなったことは確かである。ただ、それでもやはり、多忙な社会人の学び直しのうえで、距離の克服が大きな課題であることは間違いないだろう。
では、この距離を克服するための手段として、オンライン以外に採りうる方法はないだろうか。そのひとつの試みが、来ていただくのが大変であればこちらからお訪ねしてみよう、という本企画である。距離に悩まされた学芸リカプロを発展的に継承するかたちで、2022年度より、北海道大学プラス・ミュージアム・プログラムがはじまった。この新しいプログラムでは、すっかり身近なものになったオンラインでの事業公開に積極的に取り組む一方で、プログラムの実施者であるわたしたちが、北海道内のさまざまなミュージアムや関係先をお訪ねしてキーパーソンからお話をうかがうというインタビュー・シリーズを試みている。
各ミュージアムが直面している課題には、地域ごとの特性や個別の事情に根差した難しさがあるに違いない。運営体制や携わる関係者も一様ではないだろう。そうした複雑さを、「外からの」、あるいは「上からの」理論や解決法でまとめようとすることには、やはり無理があるのではないか。各地の現場を訪ね、個々の課題やそれに対する取り組みに関する知見を集め、ワークショップ等のかたちで共有し、関係者同士での議論に資することはできないか。そのような思いからはじまったインタビュー・シリーズである。端的に言えば、ミュージアムを訪ね歩く、キャラバンのようなイメージだ。
インタビューには、本学の卓彦伶特任准教授をはじめとして、北海道大学プラス・ミュージアム・プログラムの事業を担当する教員があたる。インタビューの成果は、動画コンテンツとしてまとめ、今後のわたしたちのプログラムに活用していくことを予定している。また、本冊子のような紙媒体やウェブサイトでも、情報の発信と共有に努めたい。加えて、わたしたちのプログラム全体が、「外からの」あるいは「上からの」目線に陥ることがないよう、今後の事業内容の立案にもインタビューから得られた成果をフィードバックしていくことが大切になってくるだろう。
最後に、この短い文章のタイトルについて、一言しておきたい。この文章のタイトルは、少し変な言葉かもしれないが、「なかがき」としてみた。インタビュー・シリーズがはじまる前に、予め置かれている文章であれば、「まえがき」とするのが筋だろう。逆に、一連のインタビューがすべて終了したあとであれば「あとがき」とするのがよさそうだ。しかし、いまはまだ、インタビュー・シリーズは旅の途上にある。その意味で、「まえがき」でもなく「あとがき」でもない、今後につながっていくはずのひとつのステップとして、「なかがき」と名づけてみた次第である。インタビューは続く。ゴールはまだ見えそうにない。北海道は広いから。そして、その広い北海道で行われている数多のミュージアムの魅力的な取り組みは、まだまだ汲みつくすことができそうにないからである。