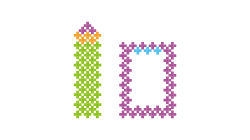
「見ること」と「話すこと」
佐々木亨

浦幌町立博物館は、浦幌を中心とする東十勝や白糠丘陵一帯の歴史、文化、自然史に関する資料を収集・調査し、展示している。自然史資料から考古資料、民俗資料まで、地域資料を幅広く扱っている地域博物館である。今回のインタビューでは、同館の持田誠学芸員にお話を伺った。
身の回りで困ったことや調べたいことがあった場合、地域の人々が気軽に相談できるよう、様々な形で対応することをミュージアムの基本的な姿勢としている。図書館が併設された複合施設にあるため、相談は図書館を通じても受け付けており、地域の人々から日常的に利用されている。名前の分からない石を拾った場合や、庭で珍しい鳥が死んでいた場合、あるいは先祖の話や家の片付けで出てきた古い写真についての相談など何でも受け付ける。相談者の中で多いのは高齢者で、自分の家から出てきた古いものや町の歴史に関する相談が多く寄せられるほか、小学生からは身近なことや学校の授業に関連したことを相談に持ち込んでくることも多いという。
どこに相談したらいいかわからないようなことをミュージアムに持ち込んで、ミュージアムを介して色々なことを解決していくというような空気感が作られている。
持田氏は地域の多様な課題に対して「自分自身もまちの一員になるということが非常に重要」とし、博物館内部と外部での活動を通じて積極的にかかわっていく姿勢を示した。
浦幌町では過疎化や高齢化が大きな地域課題になっているなか、これらの課題に対してミュージアムが直接的な政策提言をすることは難しい。最近、移住者や地域おこし協力隊などの若者によってまちを盛り上げるためのイベントが開催されている。これらの地域活性化につながる取り組みの企画・運営にミュージアムも関わって協力している。また、観光振興という視点からも町の魅力を広く知ってもらうために、浦幌町と隣接する豊頃町が地元の商工会、観光協会や帯広地域の色々な業界と協力して、東十勝ロングトレイルという浦幌町、豊頃町の自然や歴史を見て回る観光ツアーを年に数回企画している。この事業の企画立案に浦幌町立博物館も関わっており、地域資源を新しく見つけて発信していくための地域資料を提供する役割を担っている。
社会教育施設として、ミュージアムは日常的に地域の各年齢層の学びの欲求に応えるために講座形式の事業を展開している。その他には、不登校や学校に馴染めない子供たちが興味を持ったことについて個別に相談を受け、その子どもたちの興味に応じた資料や話題を提供することで、再び学校に通う機会作りの支援も行われている。

浦幌町立博物館は2015年の夏から毎月第1土曜日に豊北海岸で「豊北植物調査会」を開催している。地域の人々と一緒に植物フェノロジー観測を行ってきた7年間のデータが蓄積された。持田氏は現在、得られたデータを環境省の生物多様性センターの「モニタリングサイト1000」に提供することを検討している。これにより、地域の人たちが自分たちの地域について調べてきたことが広く社会に活用され、モチベーションも上がるという。
また、豊北海岸は漁業を営む漁師たちが利用する場所でもあり、定置網を傷めないように漁師たちは重機を使い、毎年海岸に打ち上げられた流木を撤去している。しかし、この作業は海岸の希少な原生植物を傷つけてしまうことになる。そこで、環境省の「モニタリングサイト1000」に登録することによって、海岸の姿を様々な立場の人と情報共有をしながら、豊北海岸の資源を100年後に伝えていくための意見交換のきっかけになることを期待している。
持田氏は、地域産業と自然環境保全の調和を目指すために、ミュージアムが長年にわたって蓄積してきた情報を通じて話し合いの場を作り、助言・提案を行っていく姿勢を改めて示した。
(執筆:卓彦伶)
取材日:2023年1月13日