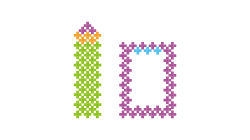
「見ること」と「話すこと」
佐々木亨

1985年の開館以来、長らく市民に親しまれてきた苫小牧市博物館は、2013年にリニューアル・オープンする際に展示室を増設して、名称を「苫小牧市美術博物館」と改めた。郷土の歴史や自然を扱う博物館としての従来の機能に加えて、さらに、「美術館」としての機能を強化することにしたのである。今回は、同館で美術を担当する学芸員の細矢久人氏と立石絵梨子氏にお話をうかがい、美術館という新たな役割を付与されたミュージアムと地域社会とのかかわり方について、教えていただいた。
リニューアルによってもたらされた新しい美術館。ただ、インタビューの中でお二人がまず口にされていたのは、そうした新しさの前に存在していたという、「下地」ないしは「素地」についてだった。苫小牧市美術博物館は、専門的な美術館としては、約10年の歴史をもつ。しかし、それ以前に、苫小牧市博物館時代の蓄積があったことが実は極めて重要だったと両氏は口を揃えるのである。
立石氏が教えてくださった一例は、リニューアル・オープンよりはるか以前、1986年に開始されて現在まで続く、「大学講座」という同館のレクチャーシリーズである。40年近くにわたる講座には今でも毎年多くの申し込みがあるという。年度の最初に入学式を、最後には卒業式を行うだけでなく、出席回数や参加年数に応じて「学士」「修士」「博士」の学位も授与される。こうした息の長い活動によって、ミュージアムが学びたいという人びとの願いに応え、地域の暮らしの中に位置づけられてきたという点は、見逃せない。
また、細矢氏は、美術館機能が付与されて再出発した苫小牧市美術博物館だが、美術以外の専門家と館内で連携できる点も、同館の大きな特色だという。ごく一例だが、たとえば現代アーティストが地域のことをリサーチして作品を制作しようとする際に、歴史や考古、自然史などを専門とする学芸員の知見や、関連するコレクションの蓄積がものを言う場合が少なくないのである。
こうしたお二人のお話によって改めて気づかされるのは、美術館が突如として上から降ってきたのではないということだ。先人たちが培ってきた文化的土壌があり、現代を生きる市民の切実な願いがあり、苫小牧市博物館時代の知見やコレクションの蓄積がある。そのうえにはじめて、現在の新しい美術館が根を下ろすことができているのである。
こうした蓄積の上に立ちながら、同館はさらに、さまざまな新しい歴史を積み重ねはじめている。教えていただいた取り組みのひとつは、地域の子どもたちが参加する「子ども広報部 びとこま」という活動である。リニューアル・オープンの少し前から始まり、現在まで続いている。ミュージアムの広報紙「びとこま」を編集して展覧会の魅力を子どもの目線で発信したり、子どもたちの会話から生まれた作品解説カードを展示室内で紹介したりと、幅広く活動してきた。立石氏によれば、ここでポイントになるのは活動に参加するアーティストの存在だという。もともとこの活動は、苫小牧市在住のアーティスト・藤沢レオ氏と氏が参画するNPO法人樽前artyプラスが主導し、ミュージアムと一緒になって行ってきたものである。子どもたちにとっては、いつも触れ合っている大人とは少し違う、アーティストという存在が重要なのだろうと立石氏は述べていた。普段の学校生活からは離れ、教室とは別のコミュニティの中に置かれ、アートやアーティストという不思議に出会う。そこには確かに、ミュージアムならではの、風通しの良い遊びと学びがありそうだ。
もうひとつ、同館の取り組みで特筆に値すると思われるのは、主に細矢氏が手がけてきた企画展「NITTAN ART FILE」シリーズである。2015年に第1回展を実施し、2022年の第4回展まで続いてきた。地域の作家、地域にゆかりのある作家を中心に、毎回数名の現代アーティストを紹介する意欲的な試みである。細矢氏は、現代美術はどうしても好き嫌いが分かれ、ときとして人びとを二分してしまうこともあるという。しかしその一方で、見慣れた「地元」をアーティストの目線で異化して提示することの意義は、氏が指摘するとおり、決して小さなものではない。本シリーズ展は、アートによって分断ではなく対話をもたらそうとする、同館を代表する継続的な試みだと言えるだろう。
ちなみに細矢氏によれば、苫小牧市は「ほどよいサイズ感」をもち、市民や地域とも「ほどよい距離感」をとりやすいそうである。国立や都道府県立のミュージアムほどの大きさがないからこそ、街や人にフィットする活動が比較的自由に出来るということだろう。細矢氏も立石氏も、ともに、より大きな都道府県立のミュージアムでの勤務経験をもつ。そうした経験を踏まえつつ、現在は、街とミュージアムとの心地の良いバランスを楽しんでおられるように感じられた。

インタビューの最後に、苫小牧市美術博物館はどのような場所なのだろうか、何かに喩えることはできるだろうかとお尋ねしてみた。しばらく悩まれた後で立石氏がおっしゃったのは、博物館は博物館、美術館は美術館であって、他のものに喩えることは難しいという回答だった。確かに、何に喩えてみたところで、それはおそらく、ミュージアムのある一側面を強調することにしかならないだろう。博物館らしさ、美術館らしさを掘り下げる。博物館の仕事、美術館の仕事を突き詰める。それこそが結局は、他の何かでは代替することができないミュージアムならではのやり方で、新しい風を地域に吹き込むことにつながるのかもしれない。

(執筆:今村 信隆)
取材日:2023年2月22日